ゲーム開発の1つの醍醐味である美麗なCGグラフィックス。
現在はゲームエンジンが担う部分も大きいですが、それを活用するため、またゲーム制作・CGの根幹を理解するために、ゲームグラフィクスの知識が必要となります。
そんな一段上のゲーム開発をするための、「ゲームグラフィックス(CG)」に関する書籍を、人気・高評価のおすすめ本として以下でまとめて紹介していきます。
発売したて・発売予定の新書をピックアップ
技術書は情報の鮮度も重要、人気ランキングの前に新しい書籍もチェックしておきましょう。
- 2021/10/12発売 「Direct3D12 ゲームグラフィックス実践ガイド」
- 2021/12/01発売 「HTMLグラフィックスプログラミング―初心者のための画像の操作からゲーム開発まで」
- 2022/08/31発売 「リアルタイムグラフィックスの数学 ― GLSLではじめるシェーダプログラミング」
- 2023/08/18発売 「画像生成系AI Stable Diffusionゲームグラフィックス自動生成ガイド」
- 2023/11/04発売 「Unreal Engine 5ではじめる! 3DCGゲームワールド制作入門」
- ゲームグラフィックスの本 人気ランキング/10冊詳細
- ゲームグラフィックス 2020 CGWORLD特別編集版
- ゲームグラフィックス 2017 CGWORLD特別編集版
- ゲームグラフィックス 2016 CGWORLD特別編集版
- Unity 3Dゲーム開発ではじめるC#プログラミング impress top gearシリーズ
- ゲーム制作者になるための3Dグラフィックス技術 改訂3版
- [増補改訂]GPUを支える技術 ――超並列ハードウェアの快進撃[技術基礎] WEB+DB PRESS plus
- リアルタイムグラフィックスの数学 ― GLSLではじめるシェーダプログラミング
- DirectX 12の魔導書 3Dレンダリングの基礎からMMDモデルを踊らせるまで
- Unity C# ゲームプログラミング入門 2020対応
- HLSL シェーダーの魔導書 シェーディングの基礎からレイトレーシングまで
- ゲームグラフィックスの本 最新・高評価のおすすめの5冊
- ゲームグラフィックス参考書「新書一覧(2021年、2022年刊行)」
- ゲームグラフィックス参考書「Kindle Unlimited 読み放題 人気本ランキング」
- 動画編:本より高コスパ?「Udemy ゲームグラフィックス おすすめ講座」
- 関連:ゲーム開発に関する参考書
ゲームグラフィックスの本 人気ランキング/10冊詳細
以下が「ゲームグラフィックスの本」人気ランキングと人気の10冊詳細です。
ランキングはAmazonの書籍売上ランキングに基づき毎日更新されています。
| Rank | 製品 | 価格 |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Unity 3Dゲーム開発ではじめるC#プログラミング impress top gearシリーズ... 発売日 2021/08/23 Harrison Ferrone, 吉川 邦夫 (インプレス) Kindle Unlimited対象 総合評価 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | [ゲーム&モダンJavaScript文法で2倍楽しい]グラフィックスプログラミング入門——リアルタイムに動く画面を描く。プログラマー直伝の基... 発売日 2020/01/11 杉本 雅広 (技術評論社) 総合評価 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ゲームグラフィックス 2013 CGWORLD特別編集版 (Works books) 発売日 2013/09/09 久代 忠史, 高木 貞武, 宮田 悠輔, オガワコウサク(有限会社グリグリ) (ワークスコーポレーション) 総合評価 | |
20 |
ゲームグラフィックス 2020 CGWORLD特別編集版
●収録タイトル
・仁王2
・ポケットモンスター ソード・シールド
・ドラゴンボールZ KAKAROT
・グランブルーファンタジー ヴァーサス
・ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス
・新サクラ大戦
・龍が如く7 光と闇の行方
・ASTRAL CHAIN
・CODE VEIN
・SAMURAI SPIRITS
・BLADE XLORD―ブレイドエクスロード―
・マジカミ
※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
↓全て表示↑少なく表示
内容サンプル


目次
龍が如く7 光と闇の行方
新サクラ大戦
仁王2
ポケットモンスター ソード・シールド
ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス
SAMURAI SPIRITS
ASTRAL CHAIN
グランブルーファンタジー ヴァーサス
CODE VEIN)
SMARTPHONE GAME(BLADE XLORD-ブレイドエクスロードー
マジカミ)
↓全て表示↑少なく表示
Users Voice
内容サンプル


ゲームグラフィックス 2017 CGWORLD特別編集版
※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
内容サンプル


Users Voice
内容サンプル


ゲームグラフィックス 2016 CGWORLD特別編集版
今年度版では、PS4などハイスペックな今世代機向けやアーケードの人気タイトルを豊富にラインナップしました!
※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
内容サンプル


目次
Game Making(ストリートファイター5
GUILTY GEAR Xrd-REVELATOR-
ガンスリンガーストラトス3
DARK SOULS 3
艦これアーケード
イグジストアーカイヴ
聖闘士星矢ソルジャーズ・ソウル
バイオハザードアンブレラコア
NARUTO-ナルトー疾風伝ナルティメットストーム4)
↓全て表示↑少なく表示
Users Voice
内容サンプル


Unity 3Dゲーム開発ではじめるC#プログラミング impress top gearシリーズ
(著)Harrison Ferrone, 吉川 邦夫
発売日 2021/08/23
※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
購入前にお使いの端末で無料サンプルをお試しください。
↓全て表示↑少なく表示
内容サンプル


目次
第2章 プログラミングの構成要素
第3章 変数と型とメソッドの世界
第4章 制御の流れとコレクション
第5章 クラスと構造体とOOP
第6章 Unityに挑む
第7章 動きとカメラ制御と衝突
第8章 ゲームのメカニズムを記述する
第9章 基本的なAIと敵の動き
第10章 再び、型とメソッドとクラスについて
第11章 スタックとキューとハッシュセット
第12章 ジェネリック、デリゲート、イベント、例外処理など
第13章 C#とUnityの旅はまだ続く
↓全て表示↑少なく表示
Users Voice
内容サンプル


著者略歴
フリーランスのソフトウェア開発者、インストラクター、テクニカルエディター。米国イリノイ州シカゴ生まれ。小さなスタートアップ企業やフォーチュン500企業で数年間をiOS開発者として過ごす。現在は、Microsoftで技術文書の作成、LinkedIn LearningやPluralsightで教育用コンテンツの作成、Ray WenderlichのWebサイトで技術編集を行っている。2013年からUnityを使ってゲームやアプリケーションを開発し、2016年からはさまざまな学習プロバイダー向けの教育コンテンツを作成している
吉川邦夫(ヨシカワクニオ)
1957年生まれ。ICU(国際基督教大学)卒。おもに制御系のプログラマとして、ソフトウェア開発に従事した後、翻訳家として独立。英文雑誌記事の和訳なども手掛ける。訳書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
↓全て表示↑少なく表示
ゲーム制作者になるための3Dグラフィックス技術 改訂3版
2013年に刊行の『増補改訂版(第2版)』をさらに改訂!!
2013年以降のゲームグラフィックス技術情報も網羅してアップデート。新規追加章「トゥーン・シェーディング」では、今注目のテレビアニメ調表現技術を解説!
ゲーム開発において必須となる3Dグラフィックスの基礎知識から、新旧のゲーム開発向け3Dグラフィックス技術の概要までを広く浅く学べる1冊。本文中には実際のゲーム画面や開発画面・図版を多数掲載しており、開発初心者の人や学生でも分かりやすく解説しています。
★2021年5月:第1版第2刷相当へデータ更新済★
▼目次▼
Chapter 1 リアルタイム3Dグラフィックス技術の進化の系譜
Chapter 2 3Dグラフィックスの概念とレンダリングパイプライン
Chapter 3 微細凹凸表現の基本形「法線マップ」とその進化形
Chapter 4 動的影生成の主流「デプスシャドウ技法」とその進化形
Chapter 5 ジオメトリシェーダとは何か
Chapter 6 DirectX 11のテッセレーション
Chapter 7 HDRレンダリング
Chapter 8 水面表現の仕組み
Chapter 9 人肌表現の仕組み
Chapter 10 大局照明技術
Chapter 11 トゥーン・シェーディング
※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
購入前にお使いの端末で無料サンプルをお試しください。
↓全て表示↑少なく表示
内容サンプル


目次
2 3Dグラフィックスの概念とレンダリングパイプライン
3 微細凹凸表現の基本形「法線マップ」とその進化形
4 動的影生成の主流「デプスシャドウ技法」とその進化形
5 ジオメトリシェーダとは何か
6 DirectX 11のテッセレーション
7 HDRレンダリング
8 水面表現の仕組み
9 人肌表現の仕組み
10 大局照明技術
11 トゥーン・シェーディング
↓全て表示↑少なく表示
Users Voice
内容サンプル


著者略歴
テクニカルジャーナリスト。東京工芸大学特別講師(現職)および工学院大学特任教授(2020年4月より)。PC、ゲーム機、映像デバイス、自動車のハードウェア技術動向のほか、ゲーム開発、AI・ディープラーニングなどのソフトウェア関連技術の記事執筆を手掛ける。2005年よりマイクロソフトMost Valuable Professional AwardのEntertainment-XNA/Xbox/DirectX部門を15年連続受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
↓全て表示↑少なく表示
[増補改訂]GPUを支える技術 ――超並列ハードウェアの快進撃[技術基礎] WEB+DB PRESS plus
(著)Hisa Ando
発売日 2021/03/16
GPUのしくみに焦点を当てた技術解説書。
3Dグラフィックス、AI/マシンラーニング、モバイル、IoT、ゲーム、ARなどの各種分野で、GPUの存在感はますます高まっています。また、科学技術計算の超並列計算にもGPUアクセラレータは重要な役割を担ってきました。それらの背景にあるGPUの特性および昨今の計算処理の要求とはどのようなものでしょうか。
本書では、GPUの今に主眼を置き、ハードウェアおよびソフトウェアの観点の基本事項、並列処理と計算の基礎から、内部構造、技術動向まで徹底解説。NVIDIAをはじめとした実製品の具体例、各分野での採用事例などを幅広く紹介し、現場で役立つ技術知識を厳選収録します。今回の改訂では、マシンラーニングの台頭に伴う性能改善のターゲットの変化と各社の新アーキテクチャの登場、第一線のGPU開発競争の鍵を握るスーパーコンピュータでのGPU採用状況など、今押さえておきたい話題を凝縮してお届けします。
(こんな方におすすめ)
・GPUの技術動向に関心のあるソフトウェアエンジニア、モバイルアプリ開発者、学生の方々
(目次)
第1章 [入門]プロセッサとGPU
1.1 コンピュータシステムと画像表示の基礎 ……フレームバッファ、VRAM、ディスプレイインターフェース
1.2 3Dグラフィックスの歴史 ……文字から図、2D、3Dへ。高品質とリアルタイム
1.3 3Dモデルの作成 ……パネル、座標、配置、光
1.4 CPUとGPUの違い ……プロセッサも適材適所
1.5 ユーザーの身近にあるGPUのバリエーション ……SoC、CPUチップ内蔵、ディスクリートGPU
1.6 GPUとおもな処理方式 ……メモリ空間、描画時のGPUメモリ確保方式、並列処理
1.7 まとめ
第2章 GPUと計算処理の変遷
2.1 グラフィックスとアクセラレータの歴史 ……ゲーム機、PCグラフィックス
2.2 グラフィックスボードの技術 ……2Dの背景+スプライト、BitBLT、2D/2.5D/3Dグラフィックアクセラレータ
2.3 GPUの科学技術計算への応用 ……ユニファイドシェーダ、倍精度浮動小数点演算、プログラミング環境
2.4 並列処理のパラダイム ……基本、MIMD/SIMD/SIMTの違い
2.5 まとめ
第3章 [基礎知識]GPUと計算処理
3.1 3Dグラフィックスの基本 ……OpenGLのレンダリングパイプラインを例に
3.2 グラフィックス処理を行うハードウェアの構造 ……Intel HD Graphics Gen 9 GPUの例
3.3 [速習]ゲームグラフィックスとGPU ……ハードウェアとソフトウェア、進化の軌跡 ◉特別寄稿 西川 善司
3.4 科学技術計算、ニューラルネットワークとGPU ……高い演算性能で用途が拡大
3.5 並列計算処理 ……プロセッサのコア数の増加と、計算/プログラムの関係
3.6 GPUの関連ハードウェア ……メモリ容量、バンド幅、CPUとの接続、エラーと対策
3.7 まとめ
第4章 [詳説]GPUの超並列処理
4.1 GPUの並列処理方式 ……SIMDとSIMT
4.2 GPUの構造 ……NVIDIA Turing GPU
4.3 AMDとArmのSIMT方式のGPU ……AMD RDNAアーキテクチャとArm Bifrost GPU
4.4 GPUの使い勝手を改善する最近の技術 ……ユニファイドメモリ、細粒度プリエンプション
4.5 エラーの検出と訂正 ……科学技術計算用途では必須機能
4.6 まとめ
第5章 GPUプログラミングの基本
5.1 GPUの互換性の考え方 ……完全な上位互換は難しい状況
5.2 CUDA ……NVIDIAのGPUプログラミング環境
5.3 OpenCL ……業界標準のGPU計算言語
5.4 GPUプログラムの最適化 ……性能を引き出す
5.5 OpenMPとOpenACC ……ディレクティブを使うGPUプログラミング
5.6 まとめ
第6章 GPUの周辺技術
6.1 GPUのデバイスメモリ ……大量データを高速に供給
6.2 CPUとGPU間のデータ伝送 ……PCI Express関連技術、NVLink、CAPI
6.3 まとめ
第7章 GPU活用の最前線
7.1 ディープラーニングとGPU ……ニューラルネットワークの基本から活用事例まで
7.2 3DグラフィックスとGPU ……広がる3D事例
7.3 スマートフォン向けSoC ……機能向上と電池や消費電力とのバランス
7.4 スーパーコンピュータとGPU ……高い演算性能を求めて
7.4 まとめ
第8章 ディープラーニングの台頭とGPUの進化
8.1 ディープラーニング用のハードウェア ……数値計算の精度と性能
8.2 各社のAIアクセラレータ ……TPU、Tensorコア、Efficiera、Goya/Gaudi、MLプロセッサ、Wafer Scale Engine
8.3 ディープラーニング/マシンラーニングのベンチマーク ……MLPerfの基本
8.4 エクサスパコンとNVIDIA、Intel、AMDの新世代GPU ……最先端のコンピュータが牽引する新技術
8.5 今後のLSI、CPUはどうなっていくのか? ……半導体の進歩、高性能CPU
8.6 GPUはどうなっていくのか ……さらなる進化の方向性
8.7 まとめ
↓全て表示↑少なく表示
内容サンプル


目次
## 1.1 コンピュータシステムと画像表示の基礎 ……フレームバッファ、VRAM、ディスプレイインターフェース
◆Column プロセッサの構造と動き
## 1.2 3Dグラフィックスの歴史 ……文字から図、2D、3Dへ。高品質とリアルタイム
## 1.3 3Dモデルの作成 ……パネル、座標、配置、光
## 1.4 CPUとGPUの違い ……プロセッサも適材適所
◆Column 整数と浮動小数点数
GPUは、並列に実行できない処理は苦手
## 1.5 ユーザーの身近にあるGPUのバリエーション ……SoC、CPUチップ内蔵、ディスクリートGPU
## 1.6 GPUとおもな処理方式 ……メモリ空間、描画時のGPUメモリ確保方式、並列処理
## 1.7 まとめ
◆Column プロセッサと半導体の世代 ……24nm世代、16nm世代... 「GxxMxx」表記
# 第2章 GPUと計算処理の変遷
## 2.1 グラフィックスとアクセラレータの歴史 ……ゲーム機、PCグラフィックス
## 2.2 グラフィックスボードの技術 ……2Dの背景+スプライト、BitBLT、2D/2.5D/3Dグラフィックアクセラレータ
## 2.3 GPUの科学技術計算への応用 ……ユニファイドシェーダ、倍精度浮動小数点演算、プログラミング環境
◆Column ムーアの法則と並列プロセッサ
## 2.4 並列処理のパラダイム ……基本、MIMD/SIMD/SIMTの違い
◆Column ARMv7のプレディケート実行機能
## 2.5 まとめ
# 第3章 [基礎知識]GPUと計算処理
## 3.1 3Dグラフィックスの基本 ……OpenGLのレンダリングパイプラインを例に
## 3.2 グラフィックス処理を行うハードウェアの構造 ……Intel HD Graphics Gen 9 GPUの例
## 3.3 [速習]ゲームグラフィックスとGPU ……ハードウェアとソフトウェア、進化の軌跡 ・特別寄稿 西川 善司
## 3.4 科学技術計算、ニューラルネットワークとGPU ……高い演算性能で用途が拡大
## 3.5 並列計算処理 ……プロセッサのコア数の増加と、計算/プログラムの関係
## 3.6 GPUの関連ハードウェア ……メモリ容量、バンド幅、CPUとの接続、エラーと対策
## 3.7 まとめ
# 第4章 [詳説]GPUの超並列処理
## 4.1 GPUの並列処理方式 ……SIMDとSIMT
## 4.2 GPUの構造 ……NVIDIA Turing GPU
◆Column ディープラーニングの計算と演算精度
◆Column RISCとCISC
## 4.3 AMDとArmのSIMT方式のGPU ……AMD RDNAアーキテクチャとArm Bifrost GPU
## 4.4 GPUの使い勝手を改善する最近の技術 ……ユニファイドメモリ、細粒度プリエンプション
## 4.5 エラーの検出と訂正 ……科学技術計算用途では必須機能
◆Column ACEプロトコルとACEメモリバス
## 4.6 まとめ
# 第5章 GPUプログラミングの基本
## 5.1 GPUの互換性の考え方 ……完全な上位互換は難しい状況
## 5.2 CUDA ……NVIDIAのGPUプログラミング環境
## 5.3 OpenCL ……業界標準のGPU計算言語
## 5.4 GPUプログラムの最適化 ……性能を引き出す
## 5.5 OpenMPとOpenACC ……ディレクティブを使うGPUプログラミング
## 5.6 まとめ
# 第6章 GPUの周辺技術
## 6.1 GPUのデバイスメモリ ……大量データを高速に供給
## 6.2 CPUとGPU間のデータ伝送 ……PCI Express関連技術、NVLink、CAPI
## 6.3 まとめ
◆Column AMD HIP
# 第7章 GPU活用の最前線
## 7.1 ディープラーニングとGPU ……ニューラルネットワークの基本から活用事例まで
## 7.2 3DグラフィックスとGPU ……広がる3D事例
## 7.3 スマートフォン向けSoC ……機能向上と電池や消費電力とのバランス
## 7.4 スーパーコンピュータとGPU ……高い演算性能を求めて
## 7.4 まとめ
◆Column Apple M1とそのGPU
# 第8章 ディープラーニングの台頭とGPUの進化
## 8.1 ディープラーニング用のハードウェア ……数値計算の精度と性能
## 8.2 各社のAIアクセラレータ ……TPU、Tensorコア、Efficiera、Goya/Gaudi、MLプロセッサ、Wafer Scale Engine
◆Column RoCE ……Remote DMA on Converged Ethernet
## 8.3 ディープラーニング/マシンラーニングのベンチマーク ……MLPerfの基本
## 8.4 エクサスパコンとNVIDIA、Intel、AMDの新世代GPU ……最先端のコンピュータが牽引する新技術
## 8.5 今後のLSI、CPUはどうなっていくのか? ……半導体の進歩、高性能CPU
## 8.6 GPUはどうなっていくのか ……さらなる進化の方向性
## 8.7 まとめ
↓全て表示↑少なく表示
Users Voice
内容サンプル


著者略歴
↓全て表示↑少なく表示
リアルタイムグラフィックスの数学 ― GLSLではじめるシェーダプログラミング
本書はリアルタイムグラフィックスの基本を理解するための解説書です。
リアルタイムグラフィックス、つまり「即時に生成される」グラフィックスはいまやゲームからビデオチャットまで広く利用されており、多くの方が目にするものになっています。この技術の根本には数学があり、数学的知識を身につけることで、多様なグラフィックスを生み出すコードの中身、グラフィックス生成のしくみを、きちんと理解できるようになります。
ゼロからしっかり理解したいと考える方に、本書は断然おすすめです。
(こんな方におすすめ)
・多様なグラフィックスを生み出すコードの中身、グラフィックス生成のしくみをゼロからしっかり理解したいと考える方
(目次)
第0章 Hello World
0.1 OpenGL,WebGL,GLSLについて知っておくべき最小限のこと
0.2 フラグメントカラー
0.3 ビューポート解像度とフラグメント座標
第Ⅰ部 アート・オブ・ノイズ
第1章 補間
1.1 線形補間とグラデーション
1.2 階段関数によるポスタリゼーション
1.3 極座標を使ったマッピング
第2章 疑似乱数
2.1 レガシー
2.2 進数表示とビット演算
2.3 ビット演算を使ったハッシュ関数
第3章 値ノイズ
3.1 値ノイズの構成法
3.2 グラデーションの滑らかさと微分
3.3 偏微分と勾配
第4章 勾配ノイズ
4.1 勾配ノイズの構成法
4.2 パーリンノイズ
第5章 ノイズの調理法
5.1 再帰
5.2 画像処理
第Ⅱ部 距離がつくりし世界
第6章 胞体ノイズ
6.1 第1近傍距離とボロノイ分割
6.2 胞体ノイズの構成
第7章 距離とSDF
7.1 2次元SDF
7.2 物差しを変える
第8章 3Dレンダリング
8.1 天地創造
8.2 SDF形状のレンダリング
第9章 SDFの調理法
9.1 モデリング
9.2 空間の操作
↓全て表示↑少なく表示
内容サンプル


目次
疑似乱数
値ノイズ
勾配ノイズ
ノイズの調理法)
第2部 距離がつくりし世界(胞体ノイズ
距離とSDF
3Dレンダリング
SDFの調理法)
Users Voice
内容サンプル


著者略歴
1982年奈良県生まれ。大阪大学大学院理学研究科博士課程修了。博士(理学)。専修大学経営学部准教授。専門は数学(とくに複素幾何学)、および数学のCG・デジタルファブリケーションへの応用。寺院の改修事業や西陣織の研究開発など、建築やテキスタイルにおける協業にも参加している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
DirectX 12の魔導書 3Dレンダリングの基礎からMMDモデルを踊らせるまで
一歩ずつ進めれば怖くない。
「DirectX 9~11に比べて超高機能/高性能だと聞いたけれど、
複雑すぎて何をしているかわからない」
「ゲームエンジンのメンテナンスをするために、
最新のDirectXの基礎を知りたい」
「フルスクラッチでMMDのモデルを
表示/アニメーションさせてみたい」
そんなC++プログラマーに向けた、
DirectX 12の「導きの書」がついに登場!
◆3Dグラフィックスの基礎
◆グラフィックスパイプラインとステージ
◆PMDデータの読み込みと描画
◆VMDデータの読み込みとアニメーション再生
◆IK
◆ポストエフェクト
など、本当に知りたかった
DirectX 12プログラミングの基本がこの1冊に!!
DirectXは初めてという人も、
DirectX 9や10で止まってしまっている人も、
本書を心強い相棒にして、挑戦の旅へと出掛けましょう!
内容サンプル


目次
Chapter 1 前提となる知識とDirectX 12の概略
1.1 本書で使用するC++
1.2 本書で使用する数学
1.3 初歩的なレンダリング理論
1.4 ハードウェアの基礎知識
1.5 DirectXの歴史と変化
Chapter 2 グラフィックスパイプラインとさまざまなシェーダー
2.1 グラフィックスパイプラインとは
2.2 シェーダーとは
■Part 2 実践編(1)
Chapter 3 初期化から画面クリアまで
3.1 最初のプロジェクト
3.2 ウィンドウ表示とDirect3Dの初期化
3.3 画面色のクリア
3.4 エラー対応
Chapter 4 ポリゴンの表示
4.1 グラフィックスパイプラインのおさらい
4.2 頂点情報の作成
4.3 頂点バッファー
4.4 頂点情報のコピー(マップ)
4.5 はじめてのシェーダー
4.6 シェーダーの読み込みと生成
4.7 頂点レイアウト
4.8 グラフィックスパイプラインステートの作成
4.9 ルートシグネチャ
4.10 ビューポートとシザー矩形
4.11 三角形ポリゴンを四角形にしてみる
Chapter 5 ポリゴンにテクスチャを貼り付ける
5.1 DirectX 12におけるテクスチャ
5.2 頂点情報にuv情報を追加する
5.3 シェーダーにuv情報を追加する
5.4 テクスチャデータの作成
5.5 テクスチャバッファー
5.6 ID3D12Resource::WriteToSubresource()メソッドによるデータ転送
5.7 シェーダーリソースビュー
5.8 ルートシグネチャにスロットとテクスチャの関連を記述する
5.9 描画時の設定
5.10 ピクセルシェーダーのプログラムを変更
5.11 画像ファイルを読み込んで表示する
5.12 ID3D12GraphicsCommandList::CopyTextureRegion()メソッドによる転送
5.13 d3dx12.h(CD3DX~)の導入
Chapter 6 行列による座標変換
6.1 行列の基本
6.2 定数バッファーとシェーダーからの利用
6.3 行列を変更してみる(2D編)
6.4 行列を用いて3D化してみる
6.5 回転アニメーションさせてみよう
Chapter 7 PMDの読み込みとモデルの表示
7.1 MMDのダウンロード
7.2 PMDデータとは
7.3 PMDにおける頂点データ
7.4 PMDヘッダー構造体
7.5 PMDの頂点構造体とレイアウトの準備
7.6 読み込んだ頂点データの描画
7.7 インデックスデータの読み込みと利用
7.8 法線データの表示
7.9 深度バッファーの導入
7.10 ランバートの余弦則
7.11 シェーダー側でランバートの余弦則を実装する
7.12 法線ベクトルも回転させて正しい結果を得る
Chapter 8 マテリアル(材質)
8.1 マテリアルとは
8.2 PMDファイルからマテリアルデータを読み込む
8.3 シェーダーへの転送と表示
8.4 マテリアルに合わせてテクスチャを貼る
8.5 テクスチャの有無に応じた処理
8.6 他のモデルも試してみよう
8.7 スペキュラとアンビエントの実装
8.8 テクスチャファイルがTGAやDDSの場合
8.9 トゥーンシェーディング
Chapter 9 リファクタリング
9.1 便利なクラスや構造体・マクロ
9.2 main.cppからApplicationクラスへ
9.3 用途によって簡単な分類を行う
9.4 結果としてのApplication.cpp
■Part 3 実践編(2)
Chapter 10 スキニングとアニメーション
10.1 スキニング(スキンメッシュアニメーション)
10.2 ボーン情報のロード
10.3 ツリーの構築
10.4 頂点シェーダーでボーン行列の配列を扱う
10.5 ボーン行列バッファーの作成
10.6 回転行列でモデルにポーズを付ける
10.7 MMDのアニメーションデータ(VMDファイル)
10.8 クォータニオンと回転行列
10.9 VMDデータを読み込んでポーズを付ける
10.10 VMDデータを使ったアニメーション
10.11 ベジェ曲線補間と2つの近似法
10.12 ベジェによるイーズインイーズアウトの実装
Chapter 11 インバースキネマティクス(IK)
11.1 インバースキネマティクス(IK)とは
11.2 余弦定理を用いた簡易的IK(間点が1つ)
11.3 CCD-IK(間点が複数)
11.4 2DにおけるCCD-IKの実装
11.5 PMDにおけるCCD-IK
11.6 その他VMDやIKの仕様を考慮する
Chapter 12 マルチパスレンダリング
12.1 マルチパスレンダリングとは
12.2 レンダリング先を変更しテクスチャとして利用する
12.3 単純なポストエフェクト
Chapter 13 影行列とシャドウマップ
13.1 シャドウ(影)とは
13.2 影行列を用いた地面影
13.3 シャドウマップの導入(マルチパスの応用)
■Part 4 応用編
Chapter 14 マルチレンダーターゲットとその応用
14.1 ピクセルシェーダーの出力を複数にする(色・法線)
14.2 色・法線情報によるディファードシェーディング
14.3 高輝度成分抽出とブルーム(光のもれ)
14.4 簡易的な被写界深度の実装
Chapter 15 スクリーンスペースアンビエントオクルージョン(SSAO)
15.1 アンビエントオクルージョンとは
15.2 数式から考えるアンビエントオクルージョン
15.3 スクリーンスペースアンビエントオクルージョン(SSAO)の実装
■Part 5 ライブラリ編
Chapter 16 imguiの利用
16.1 imguiとは
16.2 imguiの組み込み
16.3 imguiの活用例
Chapter 17 Effekseerライブラリの利用
17.1 Effekseerとは
17.2 Effekseerライブラリの取得と準備
17.3 Effekseerライブラリの組み込み
Chapter 18 DirectXTKの利用(文字列表示)
18.1 DirectXTKとは
18.2 DirectXTK12の入手
18.3 DirectXTKの組み込み
18.4 フォントを指定して文字列を表示する
18.5 文字セットの作成と日本語表示
↓全て表示↑少なく表示
Users Voice
内容サンプル


著者略歴
2004年から株式会社SNKで2Dゲームプログラマーとして2D格闘ゲームを制作し、2011年から学校法人麻生塾にてゲームプログラミングや数学を教える専任教員としてプログラマーを育成している。ゲームの作り方だけでなく、DirectX 12およびレイトレーシングなどグラフィックス系を中心とした授業をしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
Unity C# ゲームプログラミング入門 2020対応
※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
内容サンプル


目次
2 ゲームのデータを管理する
3 アニメーションの活用
4 ヒューマノイドを使いこなす
5 GUIを活用する
6 マルチプレイヤーゲーム
Users Voice
内容サンプル


HLSL シェーダーの魔導書 シェーディングの基礎からレイトレーシングまで
◆◆一部図版をカラーで提供しています。◆◆
光を自在に操るための
基本の技術を手に入れろ。
DirectXだけでなくUnityでも使われているシェーダー言語HLSL。
本書は、グラフィックスプログラマやテクニカルアーティストをめざす人が、
ハンズオン形式の豊富なサンプルを使って、3Dグラフィックを演出するシェーディング技術を
学ぶための教科書です。
本書では、サンプルプログラムとして、DirectX 12のコーディングをほとんど意識せず、
HLSLプログラミングに集中できるようなミニエンジンが提供されます。
シェーダーの基礎であるレンダリングパイプラインから、最新技術であるレイトレーシングまで、
本書を読めば、あなたもグラフィックスプログラマの仲間入りです!
~本書の内容~
・Chapter 1:レンダリングパイプライン入門
・Chapter 2:はじめてのシェーダー
・Chapter 3:シェーダープログラミングの基本(2)
・Chapter 4:ライティング基礎
・Chapter 5:ライティング発展
・Chapter 6:さまざまなテクスチャの利用
・Chapter 7:PBR(物理ベースレンダリング)
・Chapter 8:2D描画の基礎
・Chapter 9:発展的な2D描画
・Chapter 10:ポストエフェクト
・Chapter 11:シャドウイング
・Chapter 12:ディファードレンダリング
・Chapter 13:ディファードレンダリングとフォワードレンダリングの融合
・Chapter 14:3Dゲームで使える発展的シェーダー
・Chapter 15:コンピュートシェーダー
・Chapter 16:TBR(Tile Based Rendering)
・Chapter 17:レイトレーシング
※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。
※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。
※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。
※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
↓全て表示↑少なく表示
内容サンプル


目次
1.1 CPUとGPU
1.2 メインメモリとグラフィックスメモリ
1.3 絵が表示されるまでの流れ
Chapter 2 はじめてのシェーダー
2.1 DirectX 7.1以前のレンダリングパイプライン
2.2 シェーダーの導入
2.3 頂点シェーダー入門
2.4 ピクセルシェーダー入門
Chapter 3 シェーダープログラミングの基本
3.1 座標変換
3.2 テクスチャマッピング
3.3 複雑な3Dモデルの表示へ
Chapter 4 ライティング基礎
4.1 ライティングなしの3Dモデル表示
4.2 ライトの種類
4.3 反射:Phongの反射モデル
Chapter 5 ライティング発展
5.1 ポイントライト
5.2 スポットライト
5.3 リムライト
5.4 半球ライト
Chapter 6 さまざまなテクスチャの利用
6.1 法線マップ
6.2 スペキュラマップ
6.3 アンビエントオクルージョンマップ(AOマップ)
Chapter 7 PBR(物理ベースレンダリング)
7.1 PBRとは
7.2 ディズニーの論文によるPBR
Chapter 8 2D描画の基礎
8.1 DirectX 12で2D描画
8.2 2D表示
8.3 αブレンディング
Chapter 9 発展的な2D描画
9.1 リニアワイプ
9.2 その他のワイプ
9.3 画像の色を変化させる
Chapter 10 ポストエフェクト
10.1 オフスクリーンレンダリング
10.2 モノクロ化
10.3 ブラー
10.4 ブルーム
10.5 川瀬式ブルームフィルター
10.6 被写界深度
10.7 カメラの絞りによる六角形ブラー
Chapter 11 シャドウイング
11.1 投影シャドウ
11.2 デプスシャドウ
11.3 PCF(Percentage Closer Filtering)
11.4 VSM(Variance Shadow Maps)
11.5 カスケードシャドウ
Chapter 12 ディファードレンダリング
12.1 フォワードレンダリングとは
12.2 ディファードレンダリングとは
12.3 ディファードレンダリングのメリット
12.4 ディファードレンダリングのデメリット
12.5 ディファードレンダリング入門~拡散反射~
12.6 ディファードレンダリング入門~鏡面反射~
12.7 ディファードレンダリング入門~法線マップ~
12.8 ディファードレンダリング入門~スペキュラマップ~
Chapter 13 ディファードレンダリングとフォワードレンダリングの融合
13.1 半透明問題
13.2 ハイブリッドエンジンの実装
Chapter 14 3Dゲームで使える発展的シェーダー
14.1 レンダリングエンジン
14.2 レンダリングエンジンのカスタマイズ
14.3 輪郭線の描画
14.4 ステルス処理
14.5 ディザリング
Chapter 15 コンピュートシェーダー
15.1 GPGPUとは
15.2 コンピュートシェーダーとは
15.3 データの入力と出力
15.4 構造化バッファー
15.5 アンオーダーアクセスビューとシェーダーリソースビュー
15.6 学生の平均点を計算するプログラムを眺めてみる
15.7 合計点を出力するように改造する
15.8 標準偏差を計算する
15.9 コンピュートシェーダーの並列処理
Chapter 16 TBR(Tile Based Rendering)
16.1 ポイントライト再び
16.2 TBDR(Tile Based Deffered Rendering)
16.3 TBFR(Tile Based Forward Rendering)
Chapter 17 レイトレーシング
17.1 レイトレーシングとは
17.2 レイトレーシング法とラスタライザー法の違い
17.3 レイトレーシング超入門
17.4 テクスチャマッピング
17.5 2次反射
17.6 DirectX Raytracing(DXR)
↓全て表示↑少なく表示
Users Voice
内容サンプル


著者略歴
大阪のゲーム開発会社で13年間勤務し、国内だけでなく、海外のゲーム制作にも関わる。主にC++、DirectX、OpenGLなどを利用したコンソールゲーム機のゲーム制作で、ゲームAI、開発ツール制作、DirectXを用いたリアルタイムグラフィックプログラム、最適化などの業務を行ってきた。現在は、愛媛県のゲーム系の専門学校で、主にゲーム制作とCGプログラミングの授業を担当し、後進の育成に取り組んでいる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
↓全て表示↑少なく表示
ゲームグラフィックスの本 最新・高評価のおすすめの5冊
以下が「ゲームグラフィックスの本」最新・高評価のおすすめの5冊詳細です。
| Rank | 製品 | 価格 |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
ゲームグラフィックス 2014 CGWORLD特別編集版 (Works books)
(著)佐藤 カフジ, 高木 貞武, 武田 かおり
発売日 2014/09/17
今年度版では、PS4をはじめとする新プラットフォーム向けのタイトルや、
成長著しいモバイルゲームも採り入れたバラエティ豊かなラインナップとなっています。
●本書のポイント
・CGWORLD未掲載の新規トピックや各種素材の掲載
・小さくて見えにくかった画像を拡大表示して見やすく再編
・各ページごとに制作ツール/プラットフォーム/制作工程の3つをインデックス化
キャラクターから背景まで。モデリング、アニメーション、ライティング、エフェクトなど、
各社独自の制作ノウハウがここまでじっくり読めるのは本書だけ。
ゲーム開発関係者なら必読・必携のメイキング資料集です。
●収録タイトル
龍が如く 維新!
KNACK
真・三國無双7 with 猛将伝
D4:Dark Dreams Don't Die
アーマード・コア ヴァーディクトデイ
フリーダムウォーズ
ポケットモンスター X・ポケットモンスター Y
GUILTY GEAR Xrd -SIGN-
ガンスリンガー ストラトス2
Eden to Green
LINEフィッシュアイランド
ケリ姫スイーツ
↓全て表示↑少なく表示
内容サンプル


Users Voice
内容サンプル


ゲームグラフィックス 2018 CGWORLD特別編集版
ゲームグラフィック開発のノウハウを凝縮した事例集!
2018年版は『モンスターハンター:ワールド』(PS4/PC)を50ページを超える大ボリュームで解説!
さらに、PS4などハイスペックな今世代機や話題のPS VR、ますますクオリティの高まるアプリゲームまで
人気タイトルを幅広くラインナップしました!
●収録予定タイトル
モンスターハンター:ワールド
真・三國無双8
ソニックフォース
New みんなのGOLF
二ノ国II レヴァナントキングダム
Caligula Overdose/カリギュラ オーバードーズ
ゼノブレイド2
乖離性ミリオンアーサーVR
CARAVAN STORIES
神式一閃 カムライトライブ
●本書のポイント
CGWORLD掲載時に小さくて見えにくかった画像を拡大表示して見やすく再編
キャラクターから背景まで。モデリング、アニメーション、ライティング、エフェクトなど、
各社独自の制作ノウハウがここまでじっくり読めるのは本書だけ。
ゲーム開発関係者、ゲーム業界を目指す学生にオススメのメイキング資料集です。
↓全て表示↑少なく表示
内容サンプル


内容サンプル


ゲームグラフィックス 2016 CGWORLD特別編集版
今年度版では、PS4などハイスペックな今世代機向けやアーケードの人気タイトルを豊富にラインナップしました!
※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
内容サンプル


目次
Game Making(ストリートファイター5
GUILTY GEAR Xrd-REVELATOR-
ガンスリンガーストラトス3
DARK SOULS 3
艦これアーケード
イグジストアーカイヴ
聖闘士星矢ソルジャーズ・ソウル
バイオハザードアンブレラコア
NARUTO-ナルトー疾風伝ナルティメットストーム4)
↓全て表示↑少なく表示
Users Voice
内容サンプル


ゲームグラフィックス 2017 CGWORLD特別編集版
※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
内容サンプル


Users Voice
内容サンプル


ゲーム制作者になるための3Dグラフィックス技術 改訂3版
2013年に刊行の『増補改訂版(第2版)』をさらに改訂!!
2013年以降のゲームグラフィックス技術情報も網羅してアップデート。新規追加章「トゥーン・シェーディング」では、今注目のテレビアニメ調表現技術を解説!
ゲーム開発において必須となる3Dグラフィックスの基礎知識から、新旧のゲーム開発向け3Dグラフィックス技術の概要までを広く浅く学べる1冊。本文中には実際のゲーム画面や開発画面・図版を多数掲載しており、開発初心者の人や学生でも分かりやすく解説しています。
★2021年5月:第1版第2刷相当へデータ更新済★
▼目次▼
Chapter 1 リアルタイム3Dグラフィックス技術の進化の系譜
Chapter 2 3Dグラフィックスの概念とレンダリングパイプライン
Chapter 3 微細凹凸表現の基本形「法線マップ」とその進化形
Chapter 4 動的影生成の主流「デプスシャドウ技法」とその進化形
Chapter 5 ジオメトリシェーダとは何か
Chapter 6 DirectX 11のテッセレーション
Chapter 7 HDRレンダリング
Chapter 8 水面表現の仕組み
Chapter 9 人肌表現の仕組み
Chapter 10 大局照明技術
Chapter 11 トゥーン・シェーディング
※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
購入前にお使いの端末で無料サンプルをお試しください。
↓全て表示↑少なく表示
内容サンプル


目次
2 3Dグラフィックスの概念とレンダリングパイプライン
3 微細凹凸表現の基本形「法線マップ」とその進化形
4 動的影生成の主流「デプスシャドウ技法」とその進化形
5 ジオメトリシェーダとは何か
6 DirectX 11のテッセレーション
7 HDRレンダリング
8 水面表現の仕組み
9 人肌表現の仕組み
10 大局照明技術
11 トゥーン・シェーディング
↓全て表示↑少なく表示
Users Voice
内容サンプル


著者略歴
テクニカルジャーナリスト。東京工芸大学特別講師(現職)および工学院大学特任教授(2020年4月より)。PC、ゲーム機、映像デバイス、自動車のハードウェア技術動向のほか、ゲーム開発、AI・ディープラーニングなどのソフトウェア関連技術の記事執筆を手掛ける。2005年よりマイクロソフトMost Valuable Professional AwardのEntertainment-XNA/Xbox/DirectX部門を15年連続受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
↓全て表示↑少なく表示
ゲームグラフィックス参考書「新書一覧(2021年、2022年刊行)」
IT技術・プログラミング言語は、最新情報のキャッチアップも非常に重要、すなわち新書は要チェック。
ということで、2020年以降に発売したゲームグラフィックス参考書の新書一覧(発売日の新しい順)が以下です。
| 製品 | 価格 |
|---|---|
Unity 3Dゲーム開発ではじめるC#プログラミング impress top gearシリーズ... 発売日 2021/08/23 Harrison Ferrone, 吉川 邦夫 (インプレス) Kindle Unlimited対象 総合評価 | |
売り切れ | |
[ゲーム&モダンJavaScript文法で2倍楽しい]グラフィックスプログラミング入門——リアルタイムに動く画面を描く。プログラマー直伝の基... 発売日 2020/01/11 杉本 雅広 (技術評論社) 総合評価 | |
売り切れ | |
ゲームグラフィックス参考書「Kindle Unlimited 読み放題 人気本ランキング」
「Kindle Unlimited」は、Amazonの定額本読み放題サービス。
最近はKindle Unlimitedで読める本もどんどん増えており、雑誌、ビジネス書、実用書などは充実のラインナップ。
以下がKindle Unlimitedで読み放題となるゲームグラフィックス参考書の一覧です。
30日無料体験も可能なので、読みたい本があれば体験期間で無料で読むことも可能です。
| Rank | 製品 | 価格 |
|---|---|---|
1 | Unity 3Dゲーム開発ではじめるC#プログラミング impress top gearシリーズ... 発売日 2021/08/23 Harrison Ferrone, 吉川 邦夫 (インプレス) Kindle Unlimited対象 総合評価 | |
2 | 売り切れ |
動画編:本より高コスパ?「Udemy ゲームグラフィックス おすすめ講座」
Udemyではゲームグラフィックスを基礎から応用までトータルで学べる学習講座があります。
こちらが、セール時には2千円程度で購入可能で、講座によっては本よりコスパよく学習が可能です。
講座は、買い切り型ながら更新あり、質問可能、30日間返金も可能、という本以上の手厚いサポートがあるのが魅力。
以下の表が、ゲームグラフィックスの学習講座例。セールの場合、かなりおすすめなのでぜひトライしてみください。
| 人気 Rank | 学習コース | 評価 |
|---|---|---|
1 | Unity ゲーム開発:インディーゲームクリエイターが教える C#の基礎からゲームリリースまで【スタジオしまづ】... 発売日 2019/04/19 受講者 14,534人 通常 27,800円 現在 27,800円 | 総評価数 1742件 |
2 | Unityゲーム開発入門:Unityインストラクターが教えるマリオ風2Dアクションゲームを作成する方法【スタジオしまづ】... 発売日 2019/07/25 受講者 7,690人 通常 27,800円 現在 27,800円 | 総評価数 1176件 |
3 | 総評価数 28件 | |
4 | 総評価数 319件 | |
5 | 総評価数 208件 |
関連:ゲーム開発に関する参考書
以下ではゲーム開発全般に有用な書籍をまとめています、合わせてのぞいて見てください。
また、ゲームエンジン「Unity」「Unreal Engine 4」 に関する書籍も以下でまとめています、こちらも合わせてのぞいて見てください。
いじょうでっす。
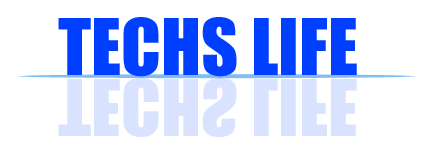






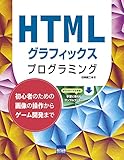

























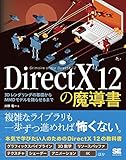
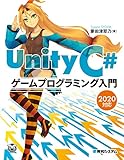
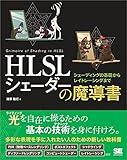


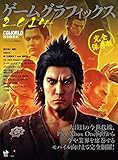





















コメント
gdmnyx